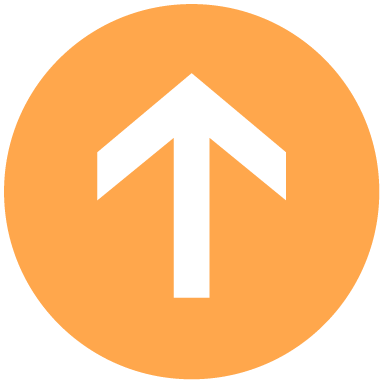和三盆とは? その歴史

奈良に旅行に出かけてきました。お水取りの行事がある時でしたので、この行事ならではのきれいな和三盆で作られた和菓子がありました。口に入れたとたんに舌の上ですぐに溶けて、とても上品でほっと癒されるやさしい味でした。
和三盆とは日本の伝統的な砂糖で、高級な和菓子などに用いられていることは知っていましたが、改めて調べてみました。
和三盆は香川県・徳島県の特産で、和白・三盆白・阿波三盆とも言われます。
原材料の甘蔗(さとうきび)は東インドが原産地といわれ、鑑真が日本に伝えたとされていますが、日本では甘蔗はうまく栽培できず、栽培が盛んになったのは江戸時代になってからでした。徳川吉宗が琉球から苗木を取り寄せ、砂糖を作ることを奨励しました。高松藩主の松平頼恭(よりたか)は、享保の改革の時に特産物をつくることと財源確保のために、平賀源内に長崎で学んだことをもとに研究させました。その後、平賀源内の門人の試行錯誤の末、日本初の三盆白という白い精糖を作り出すことに成功しました。讃岐の三盆白は、日本独特の方法で作られ、とても質の良い白砂糖だったそうです。
現在では、昔ながらの手作りの和三盆はわずかに残るだけになっていますが、添加物などは一切使用していない自然食品で、現代の砂糖より風味があります。
和三盆は、江戸時代の歴史に名を残す人たちの努力によって作られていたと知り、とても驚きました。次に食べる時には、もっとじっくり味わいたいと思います。