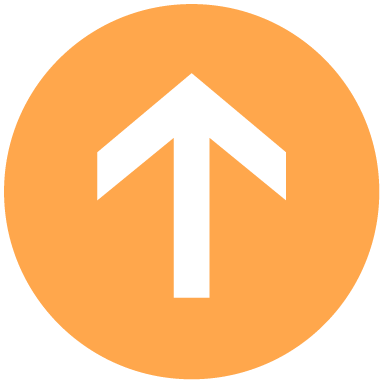みたらし団子は神社から生まれた甘辛だんご

秋が深まり、お月見の季節となりました。お月見団子はどのようにして召し上がりますか。砂糖やあんこをつけて食したり、または、みたらしにされたりするでしょうか。
みたらしとは?
みたらし団子の発祥は、上新粉を蒸して小粒の団子を作り、細い竹串に五個ずつ刺し、しょうゆをつけて焼いた素朴な串団子でした。最初の一つが人の頭、残りの四つが手足を表しているともいわれており、京都の下鴨神社の「夏越(なごし)の祓(はらえ)」に供えた神饌(しんせん)菓子でした。
名前の由来は、下鴨神社の「御手洗池(みたらしいけ)」です。神前で身を清める「みそぎ」の際に池の水面に浮かぶ水泡の形を見て、その姿を模して作られたことから「御手洗団子」と呼ばれたといわれています。神に人の姿を模した供え物を捧げ、身のけがれを清めるという信仰に基づくものです。室町時代にはすでに神社の祭礼で供えられ、江戸時代になると参拝者向けの名物として広まりました。
現在では、関西では香ばしく焼いた団子に濃いめのたれを絡め、関東ではやや甘めでとろみのあるたれが主流だそうです。地域によって味の違いはありますが、いずれも香ばしいしょうゆの香りが食欲をそそります。
団子の香ばしさは、心と体を和ませてくれます。団子を味わいながら、日本の食文化の奥行きを感じてみてはいかがでしょうか。